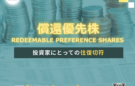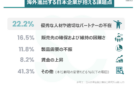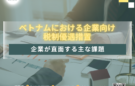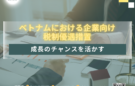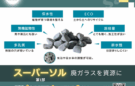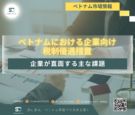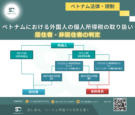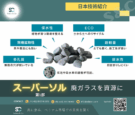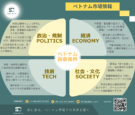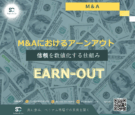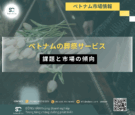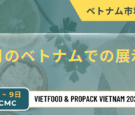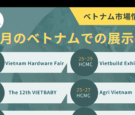【2025年最新版】日本企業が陥りやすいベトナム市場調査の落とし穴と対策

はじめに
近年、製造拠点の分散や新興国市場の開拓を目的として、多くの日本企業がベトナム市場への進出を検討しています。その際、欠かせないのが「市場調査」です。しかし、実際にベトナムでの事業展開を目指す中で、多くの日本企業が“思わぬ落とし穴”にはまり、進出後に苦戦するケースも少なくありません。
本記事では、弊社Solara & Coがこれまで多くの企業をサポートしてきた経験をもとに、日本企業がベトナム市場調査で陥りやすい典型的な失敗例とその対策をご紹介します。
落とし穴1:地域差を見落とす(ホーチミン=ベトナムと思い込む)
♦ 問題の背景
ベトナムは南北に細長く、地域ごとに文化・経済状況・消費スタイルが大きく異なる国です。
しかし多くの日本企業が、ベトナム最大の経済都市であるホーチミン市での調査や成功をもとに、そのまま他地域にも展開できると考えてしまうというミスを犯しています。
実際には、北部のハノイと南部のホーチミンでは、人々の価値観や購買行動に明確な違いがあるため、ホーチミンで成功した戦略がそのまま全国で通用するとは限りません。
♦ 地域差の具体例
| 地域 | 特徴 |
|---|---|
| ハノイ(北部) | 保守的、品質重視、伝統志向、ブランドに対する忠誠心が強い |
| ホーチミン(南部) | 新しいものに敏感、トレンドやSNSに影響されやすく、スピード重視 |
| ダナン(中部) | 観光業中心、消費性向は控えめ、所得水準は比較的低め、慎重な消費傾向 |
例えば、ハノイでは“安くて便利”より“信頼できる品質”が重視され、ホーチミンでは“おしゃれで話題性がある”ことが重視される傾向があります。
♦ 地域差を軽視することで起こる失敗例
・ホーチミンで流行した商品をそのままハノイに展開 → 「派手すぎる」「信用できない」と受け入れられず失敗
・中部にホーチミン価格をそのまま適用 → 可処分所得が合わず、売れ行きが鈍化
・SNSマーケティングを全国一律で実施 → 地域ごとに人気のKOLや話題が違い、訴求が空振りに
・店舗出店を「ホーチミンで成功したから」という理由で他都市でも展開 → 想定よりも集客に苦戦
♦ 対策
・調査は「全国調査」ではなく都市ごとに設計する:特に主要3都市(ハノイ・ホーチミン・ダナン)は必須
・地域ごとのテスト販売・ポップアップ出店を行う:現地の反応をリアルに把握
・ローカルメディアやSNSを分析し、地域別のトレンドを把握:人気の投稿内容やKOLも異なる
・現地パートナーや販売代理店と綿密に連携する:地域事情に通じたパートナーの意見は極めて重要
ベトナム市場は一枚岩ではありません。
「ホーチミン=ベトナム」ではなく、「ホーチミンはベトナムの一部」として認識することが、現地展開の成否を左右するカギとなります。
落とし穴2:現地パートナーに依存しすぎることのリスク
♦ 問題の背景
ベトナム市場において、現地パートナーとの連携は非常に重要です。しかし、その重要性ゆえに、すべてを現地任せにしてしまう日本企業も少なくありません。
「信頼しているから」「自分たちは現地のことがわからないから」として、調査や交渉、顧客開拓の多くを現地のパートナーに一任するケースがあります。これにより、情報がブラックボックス化し、自社にとって本当に必要な知見が蓄積されないまま、依存度だけが高まってしまうのです。
♦ ありがちな失敗例
・現地パートナーの紹介によるサンプル顧客に対して調査を実施 → 都合の良い回答ばかりが集まり、実態が見えない
・パートナー企業の営業方針にすべて従ってしまい、価格競争に巻き込まれる
・“信頼していた担当者”が退職し、関係がゼロからやり直しに
♦ なぜ依存が問題なのか?
・情報の偏り:パートナーの見解だけでは市場の多様性が把握できない
・透明性の欠如:顧客情報や調査ロジックが社内で共有されないため、検証や戦略修正が難しい
・自社にノウハウが蓄積されない:市場に関する知見が社内に残らず、次の展開に活かせない
♦ 対策
・第三者視点での検証を取り入れる:パートナーの情報に加え、独自または中立的なコンサルによるクロスチェックを実施
・情報をドキュメント化・共有化する:進捗、調査内容、ヒアリング記録などを社内で見える化し、再現性を高める
・段階的なパートナーシップ構築:最初から全面委託ではなく、役割を明確に分担し、少しずつ関係を深める
・現地チームや自社担当者の育成にも注力:将来的にパートナー依存から脱却できる体制を構築
「任せる」と「丸投げ」は似て非なるもの。信頼関係を大切にしつつも、自社としての主体性と戦略的な視点を持つことが、長期的な成功に繋がります。
落とし穴3:競合分析が不十分なまま参入してしまう
♦ 問題の背景
日本企業の中には「自社製品はユニークだから、現地に競合はいない」と考えて参入するケースが少なくありません。あるいは、「日系企業はまだ少ないからチャンスだ」と判断することもあります。
しかし、現地のローカル企業や韓国・中国など他国の企業はすでに激しい競争を展開しており、実際には“見えにくい競合”が多く存在します。
さらに、競合がどのような価格帯で、どんなチャネルで販売しているかを把握しないまま参入してしまうと、いざ自社製品を出しても「高すぎて売れない」「ブランドが浸透しない」といった事態になりかねません。
♦ 実際に起きたケース
日本のある化粧品メーカーは、「品質の高さ」で勝負しようと中価格帯の商品を展開しましたが、既に韓国系ブランドが同価格帯で強力なプロモーションと現地モデルの起用を展開しており、まったく歯が立たなかったというケースがあります。
♦ 競合分析が不十分なことで起こる問題
・価格設定のミスマッチ:現地市場と比べて高すぎたり、安すぎて「価値が低い」と思われる
・販路選定の誤り:競合がオンライン中心なのに、自社はオフライン重視で展開してしまう
・プロモーションの効果が薄い:競合が影響力のあるKOL(インフルエンサー)を活用している中、伝統的な広告だけでは認知が広がらない
・ブランドポジショニングの失敗:自社が想定していた“高級”や“信頼”の価値が、現地では伝わらない
♦ 対策
・現地における競合マップを作成する:価格帯、販路、強み・弱み、プロモーション戦略などを可視化
・実店舗・ECサイトの現地視察を行う:実際に競合商品がどこでどのように販売されているかを体感
・現地消費者へのインタビュー調査:競合ブランドに対する印象や選ばれる理由を聞く
・競合のSNS運用をモニタリング:投稿内容、反応、プロモーション時期などを参考に自社戦略に活かす
競合の存在を過小評価すると、**「市場がない」のではなく「他社に取られている」**という現実に直面します。ベトナム市場での競合分析は、単なる参考情報ではなく、生き残りの前提条件といえるでしょう。
落とし穴4:古い統計データや非公式情報に依存する
♦ 問題の背景
ベトナムでは、統計インフラや情報公開体制が日本ほど整っていないのが現状です。
たとえば、政府統計や業界団体のレポートは年1回の更新にとどまり、英語や日本語への翻訳も限定的です。そのため、インターネットで簡単に見つかる情報は1〜3年前のものであることが多く、日本のビジネスパーソンが古い情報をもとに現地戦略を構築してしまうリスクがあります。
また、一部のブログやニュースサイトが発信する非公式情報に頼ることで、誤解や偏った認識を持ってしまうケースも後を絶ちません。
♦ 実際のリスク
・競合環境が変化している:調査当時は競合が少なかったが、現在は多くの新規参入企業が台頭
・消費傾向が急激にシフトしている:Z世代を中心に、SNS起点での購買行動が加速中
・法規制が改正されている:過去に参照した制度がすでに廃止または大きく変更されている
・非公式なソースに依存し、意思決定にバイアスがかかる:特定のブログや古い記事のみを根拠にすることで、客観性を欠いた戦略になる
♦ 対策
・一次情報の取得を最優先に:現地の企業訪問、店頭観察、インタビューを通じたリアルな声の収集
・信頼性の高いローカルメディアを日常的にモニタリング:VietnamNet、CafeF、VNExpressなどの現地ニュースを定期チェック
・JETRO、ベトナム商工会議所(VCCI)の最新レポートを活用:翻訳された一次資料が手に入る場合は積極的に活用
・ 「最新データ」にこだわる姿勢を持つ:「今年の統計か?」「直近半年の傾向か?」を常に確認する習慣を
ベトナムのようなダイナミックに変化する市場では、「情報の鮮度」が戦略の成否を分けます。
だからこそ、古い情報に基づいた判断は、もはやリスクそのものです。
落とし穴5:表面的なデータだけで市場の全体像を判断してしまう
♦ 問題の背景
多くの日本企業が進出検討の第一歩として活用するのが「GDP成長率」「人口構成」「中間層の拡大」といったマクロデータです。確かにベトナムはASEANの中でも安定した成長を続けており、2023年のGDP成長率は5.1%、中間層は2030年までに人口の50%を超えると予測されています。
しかし、これらのデータは“ポテンシャル”を示すに過ぎず、実際の市場参入の成否には直結しません。マクロデータに基づいて「市場はある」と判断し、詳細な需要分析や競合分析を怠った結果、「思っていた以上に売れない」「すでに飽和状態だった」というケースが後を絶ちません。
♦ 実際の失敗例
ある日本の食品メーカーは、「ベトナムでは日本食人気が高まっている」「人口が増えている」という情報をもとに即席味噌汁を展開。しかし実際には、ベトナム人の食習慣や家庭調理スタイルと噛み合わず、また他国製品との価格競争にも敗れ、1年半で撤退となりました。
♦ なぜ表面的なデータだけでは足りないのか
・ニーズの深さが見えない:人口が多くても、実際に購買意欲がある層は限定的
・文化・習慣の壁:日常の購買行動・料理習慣・支払い方法などが異なる
・流通インフラの問題:特定エリアでは物流や小売網が未整備
・競合の実態がつかみにくい:現地では表に出てこない競合が存在
♦ 対策
・ミクロ視点の調査を必ず取り入れる:現地消費者の行動観察、家庭訪問調査などを実施し、「誰が」「いつ」「なぜ」買うのかを把握
・需要だけでなく“買う理由”を探る:単なるニーズの有無ではなく、購入動機や購買決定要因を明確にする
・市場の“温度感”を確認する:SNSや口コミ分析を活用し、現地のリアルなトレンドを把握
・競合マッピングを現地で実施:ショッピングモール、コンビニ、ECサイトを調査し、実際の売れ筋や価格帯を確認
このように、「データがある=市場がある」と短絡的に判断せず、数字の裏側にある生活実態や価値観にまで踏み込むことが、ベトナム市場では特に重要です。
おわりに:市場調査は“投資”である
ベトナム市場は魅力的であると同時に、情報が不透明で、文化的なギャップが大きい難しい市場でもあります。誤った情報に基づいて進出すれば、数千万〜数億円の損失に繋がる可能性もあるため、事前の市場調査こそが最大のリスクヘッジです。
弊社Solara & Coでは、日越両国の文化・商習慣を深く理解したコンサルタントが、御社のニーズに最適な市場調査プランをご提案いたします。初期調査から戦略立案、現地パートナー選定まで一貫したサポートが可能です。
「まずはベトナム市場を理解したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。